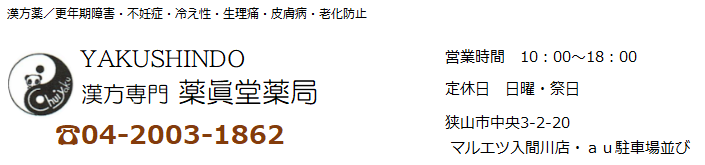紅景天の話
初めて紅景天を知ったのは2001年3月の中医臨床の特集「虚証と補剤」に単味の補益薬の研究と応用に書かれていたのが紅景天でした
チベットの高山に生育しチベットでは常用され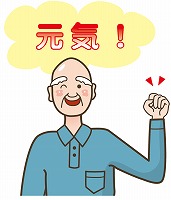 る中草薬だそうです
る中草薬だそうです
そこには以下のような効能があると書かれています
扶正固本・・・正気を扶助して身体の守りを固める
理気養血・・・気の流れを良くし血を養う
健脳益智・・・脳を健やかにして智を益す
滋補強身・・・身体を滋養し補い強く丈夫にする
その為皇帝への献上品だったそうです
「仙賜草」「高原の人参」の別名もあるそうです
なんて良い働きのある薬草があるのかと感心しました
翌年イスクラ産業から香ロゼアが新発売になりました
こちらはシベリア地方に生育するもので、チベットの紅景天と同じだそうで、ベンケイソウ科の植物でイワベンケイともいうそうです
当時、中国の中医学の認定試験を受けようと試験勉強をしていたので健脳益智を期待して飲んで見ました
眠くて頭に入って来ない時に飲んでも眠気はとれなくてうとうとしてしまいました
「コーヒーと違って眠気はとれないなぁ」と思いました
でも飲むと覚えた事が良く出てくる感じがしました
ちょうど記憶の引き出しから取り出しやすくなったような感じでした
しかも 美味しいお茶です
飲むとバラの味がします
根の部分なのに不思議ですね
紅茶に入れるとローズティーみたいになります
ただ そのまま口にいれると渋柿を口に入れたような渋さを感じるので必ずお湯に溶かしてお茶として飲んで下さい
嫌われ者も漢方
サソリ・ミミズ等嫌われ者も古代からの沢山の経験則により性味・帰経・働きなどが中薬学に記されている中薬の1つです
平肝熄風薬に分類されています
聞きなれない言葉だと思いますが、中薬学に『肝経に入って内風を平熄し肝陽を平定する薬物を平肝熄風薬という』とかいてあります
『平肝熄風薬には清肝・潜陽・鎮痙などの効能があり、高熱による意識障害・痙攣・ひきつり・後弓反張・肝陽偏亢・肝風上旋による眩暈・頭痛・顔面紅潮、はなはだしいと肝風内動による・・・・・・・。なお、虫類の薬物には通絡の効能があり、風湿痺の疼痛・しびれに応用できる』(中薬学より)
ミミズは日本でも昔から熱さましとして使われてきました
地竜という名で総合感冒薬に配合されている事もあります
子供の頃熱を出すと地竜を煎じて飲ませてもらっていました
節模様のある平たい紐みたいな感じでミミズとは知りませんでした
中薬学をみると①清熱熄風・定驚 ②精肺平喘 ③行経通絡 ④利水通淋となっています
③の行経通絡ですが経絡を行かせ通じさせるという事です
経絡という言葉は馴染みのない人も多いと思いますが、簡単に言うと人体の内と外・上と下など全身をくまなく網羅している気血を運行の通路です
不通則痛・・・通じなければ則ち痛みになるという意味ですから通じれば痛みがとれるという事になります
蠍(サソリ)の処方用名は全蠍(ぜんかつ)
①熄風止痙②活絡止痛③攻毒散結と書いてあります
毒のあるサソリですが中医学には「毒を以て毒を制す」という言葉があります
清朝末期の頃の名医 張錫純の医学折衷参西録に全蠍を使った話が出ている
顎下に時毒により生じた堅い腫脹に壁の上にいた全蠍7匹を焙って焦がし末にして黄酒で服用させ3日で腫脹が消えたとかいてあります
昔の事ではありますが、その場で手に入れて調理し治療した事に驚くと伴にこういった療法が人の暮らしの中にあったのだと感じます
これ等に加えキダ・白僵蚕・蘇合香など入った食品(星火活絡丹)が新発売になりました
詳しくはこちら↓
星火活絡丹 | 製品紹介 | イスクラ産業株式会社 (iskra.co.jp)
骨粗鬆症と骨折
骨粗鬆症と骨折は密接な関係があります
先日“今日の健康”を見ていたら整形外科の医師が「骨卒中」という衝撃的な言葉を使っていました
高齢者が背骨や足の付け根の骨折を繰り返すと寝たきりになりやすく死亡リスクも高まるといわれているそうです
骨粗鬆症で骨がもろくなっていると繰り返し骨折しやすくなります
骨がしっかりしていれば骨折しても治りも良いと思いますが骨がスカスカでは治りも悪くなります
内臓の病気によって骨密度が低下する時もありますが、一般的にはカルシウム不足やビタミンD不足 それに日光にあたらない事や運動しないので骨に負荷がかからないとかがあります
驚く事に日本人の98%がビタミンD不足だそうです
食事からの摂取が少ない事と紫外線を殆ど浴びていないという2点が主な原因だそうです
因みにシイタケやきくらげは天日干しするとビタミンDが増えるそうです
また乳製品や小魚などカルシウムもしっかりとって食事からの不足を補いましょう
骨を丈夫にするには負荷をかけるのがよくジャンプなど骨に直接刺激がいくのが良いそうですが散歩でもしっかり足をあげて歩く効果があると思います
中医学では骨粗鬆症についてどう考えるのでしょう
【腎は骨を主る、髄を生じ髄海に通じる】
つまり骨の弱りは腎の弱りといえます
五臓は相生相剋で関係しているので、腎以外の臓腑の影響を受け腎が弱る事もあります
しかし〈生長発育を主る〉腎は老化とも多いに関係しています
年をとれば程度の差はあっても誰もが腎虚になります

腎を補い筋肉や骨を強くするものに 鹿茸・鹿腎・杜仲・淫羊藿・巴戟天・桑寄生・
牛膝などあります
また熟地黄は「滋陰養血するだけでなく生精補髄生骨し、補益肝腎の要薬である」と中薬学に書かれています
腰痛・関節痛・下肢のしびれや痛みに使う独歩顆粒にも桑寄生や杜仲や牛膝が使われています
参馬補腎丸には鹿茸・鹿腎・杜仲・淫羊藿・熟地黄が使われています
養生食品の亀鹿仙に〈益腎強骨(中薬学より)〉の亀板・鹿角が使われています
老化防止や骨粗しょう症予防に漢方もお役立て下さい
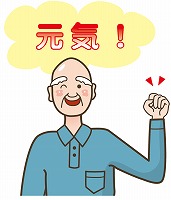 る中草薬だそうです
る中草薬だそうです